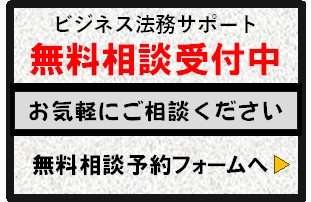会社設立時定款の作成 ~無料フォーマットも善し悪し~

会社設立の定款を作成するときに、特に難しいと感じる点はいくつかあると思います。そもそも独特の文面なので、法文書に慣れていないと、文面を起こすこと自体にかなり難儀されると思います。
定款の作成にとりかかって最初の関門になるのは、将来を見据えた事業目的の設定でしょうか。具体的すぎると後々事業が多角化した際に変更が必要になりますし、抽象的すぎると事業内容が不明確になり、登記が通らない可能性も出てきます。
次に、機関設計です。機関設計とは、会社運営に必要な機関(株式会社であれば株主総会や取締役会、監査役などの設置をどうするか。合同会社であれば、業務執行社員や代表社員をどう定めるか)を会社に基づいて定めることです。実際の経営方針に最適な機関設計を考えるのは、会社法の知識がないと難しいと感じるでしょう。
そして、資本金の額とその払込方法も悩ましい点です。いくらに設定するのが適切なのか、現物出資をする場合はその評価はどうするのかなど、法的なルールに則りつつ、会社の状況に合わせて決める必要があります。
意外と見落としがちなのが、事業年度の設定です。税務上の届け出とも関わってくるため、会社の業務サイクルや決算処理の都合などを考慮して決める必要があります。
最後に「相対的記載事項」です。インターネットで検索すれば無料フォーマットはいくらでも公開されていますし、法務局からも定款作成専用ツールが提供されていますから、手間の省略やコスト節約のため、これらを利用して作成したものを会社設立の登記申請時の書類として使うことも可能ですが、このような無料ツールを用いて作成した定款で会社を設立した場合は、当面は問題なくても、会社法における相対的記載事項に関するリスクが潜在している可能性に注意が必要です。
会社法における相対的記載事項とは、会社の実情や設立者の個別の意向に合わせて任意で定めておく事項で、定款に記載しなくてもその定款自体は無効とならないものの、その事項について効力を発生させるためには定款に記載することが必要となる事項を指します。会社法の原則とは異なる、当該会社独自のルールを定めることで、その会社の実情に合った効率的な経営を可能にします。その一例としては、代表役員を定める1、役員の死亡時にその相続人が就任できるようにするなどがあります。特に役員が一人の会社の場合、相続に関する定めについては、ちゃんと検討すべきと考えます。
無料で入手できる定款フォーマットは、あくまで汎用的な内容であって、相対的記載事項は基本的にはカバーされていません。必要な相対的記載事項が盛り込まれていなかったことで、将来、不利益を被る可能性もあります。定款作成は単なる会社設立のための書類作成ではなく、そこに書いた内容は、設立後に会社法を順守するための手順書となり、会社の将来のあり方を左右する重要な証書でもあると言えます。
- 定款に代表役員の定めがなければ、全ての役員が会社を代表する権限を有します。実際は、代表者を1名だけ定める会社が多いです。しかし、例えば3名以上の役員がいる会社で、そのうち2名を代表者にすることも可能です。 ↩︎