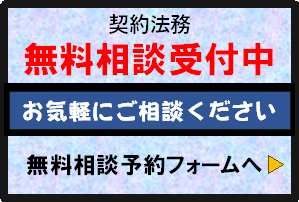契約書の「公序良俗に反する場合」って何でしょう?

契約の解除条件に「そのほか公序良俗の反する場合」という文言をよく見かけますが、この公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、何でしょうか・・・、生成AIによれば、次のとおりです。
Google Gemini の回答
「公序良俗(こうじょりょうぞく)」とは、「公の秩序(おおやけのちつじょ)」と「善良の風俗(ぜんりょうのふうぞく)」を合わせた言葉で、社会的な妥当性や道徳観を指します。法律行為が無効になる場合や、契約内容が反するなどの場合に用いられる用語です。
ChatGPTの回答
公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、日本の法律用語で、「公共の秩序」と「善良な風俗」を意味する言葉です。社会全体の基本的な道徳観や倫理観に基づいて、人々が安心して暮らせる秩序や、一般に受け入れられている常識的な行動基準を指します。
民法では、第90条~第92条で次のとおり定めています。
第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。第91条(任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。第92条(任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
条文だと堅苦しいので平たく表してみましょう。小職の個人的感想ですが、契約書を読むには充分だと思います。
第90条(非常識な行為は、具体的に当てはまる法令がなくても無効です)
非常識な契約内容などは無効です。それがなにかは、社会全体で良いとされる習慣や風習、道徳に照らして個別に判断します。
第91条(当事者同士の約束は、原則として民法より優先します)
違法、非常識な契約内容でなければ、当事者間で自由に契約内容を定めることができます。その場合、その当事者間に限り、法的に有効とみなします。
でも、法令のなかには、当事者同士の合意に関係なく、必ず守らなければならないことがあります。
第92条(慣習として定着していることは、原則として民法より優先します)
違法、非常識な契約内容でなければ、客観的に定着している慣習に則った契約内容は、その当事者間に限り、法的に有効とみなします。
でも、法令のなかには、慣習に関係なく、必ず守らなければならないことがあります。
公序良俗に反する契約内容は無効となるため、当事者はその契約に基づく権利を主張したり、義務を履行したりする必要がなくなります。これは、社会的に許容できない行為によって利益を得ることを防ぐための重要な原則です。なお、何が公序良俗に反するかは、時代や社会状況によって変化する相対的なものです。裁判所は、個々の具体的な事案に照らして、社会 の道徳観念や社会秩序を考慮し、判断を下します。