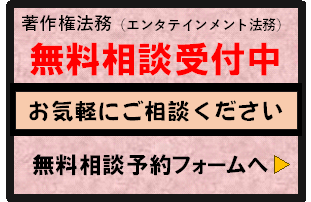なぜ人は著作権を主張するのか?~行動経済学の視点を加えて~

著作権法は、人間の独創的な知的活動から生まれた作品を保護し、創作者がその作品を独占的に利用できる権利について定めています。もし誰かのアイデアが簡単に盗用されてしまうなら、人は創造的な活動への意欲を失い、文化の発展は停滞してしまうでしょう。しかし、無制限に権利を主張できるようになってしまうと、著作権の価値自体が下落するほか、無意味な争いを多く招きかねません。したがって著作権法は、創作者の権利を守りつつ、不合理な争いを防ぎ、人類の文化発展を促進することを目的1としています。
そもそも法律で定める必要があるということは、人間の強い欲求が複雑に絡み合っているからと考えられます。それについて、行動経済学の視点を加えてみると、人が著作権を主張する根本的な理由がいくつかに分類できることが分かってきます。
行動経済学について
小職は、経済学の専門家ではありませんが、マーケティング担当者時代に「人はリスクを恐れる」という実務上の概念があり、例えば「今ならお得!」よりも「〜までに買わないと損!」という広告の方が効果が高いことを説明する理由になっていました。このように、人が重要な判断をする時に、どんな情報に左右されるかということを分析したのが、行動経済学です。
損失への強い反応
人は、自分が創作したものを所有したいという強い欲求を持っており、さらに自分が所有しているものの価値を高く評価する傾向があります。
著作権侵害は、自分が高い価値があると思う所有物を奪われるという「損失」として認識され、それが強い不快感や怒りを引き起こし、著作権を主張することで損失を回避しようとしているとすれば、行動経済学のプロスペクト理論2における損失回避性(人は損失を回避したいという強い動機を持つ)に当てはまります。
不公平感と戦略的互酬性
人は、自分の努力や貢献が正当に評価され、報酬が与えられるべきだという感情を持ちます。著作権侵害は、ときに自分の努力が不当に利用されているという「不公平感」を招きます。また、人は互いに協力し、貢献し合うことで社会が成り立っているものだと考えます。また、他者が協力的ならば自分も協力する(正の互酬性)が、非協力的ならば処罰する(負の互酬性)という戦略的互酬性の表れでもあります。
社会的認知と自己肯定感
人は、他人から認められたいという欲求を持っています。著作権を主張することは、自分の創造性を社会的に認知してもらうための手段となります。また、自分の権利を守ることは、自己肯定感を高め、尊厳を保つことにもつながります。
直感と独自基準
個人の性格、経験則などに基づいて直感的に満足できる判断(ヒューリスティック)によって生じた感情から、著作権を主張する行動が引き起こされることもあります。ときにその主張の内容には、偏った認識(認知バイアス)が含まれている場合があります。
集団心理と社会的規範
著作権侵害が横行する状況では、個人は「自分だけが損をするのは許せない」という心理から、集団的に著作権を主張するようになることがあります。また、著作権を尊重することが社会的な規範となれば、人々はそれに従うようになります。
まとめ
著作権は人類の文化の発展のために必要なものであり、著作者の財産や人格は厚く保護されるべきです。しかし、著作権侵害は、複雑な法的問題を含む場合があり、人は必ずしも合理的に判断するとは限りません。また、無制限に他者への主張を認めてしまうことのデメリットは前述のとおりです。
弁護士、弁理士、行政書士等の知的財産権に関わる法律専門家が、依頼者の思いを傾聴し、主張の基礎になっているものへの理解をもって、合理的な助言や手続きの支援をすることが、著作権保護に対する重要な役割であると考えています。
脚注
- 著作権法 「(目的)第1条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」 ↩︎
- 「プロスペクト理論」1979年にダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって提唱された、損失を過大評価し、利益を過小評価する人間の心理を表す理論。2002年ノーベル経済学賞を受賞。 ↩︎