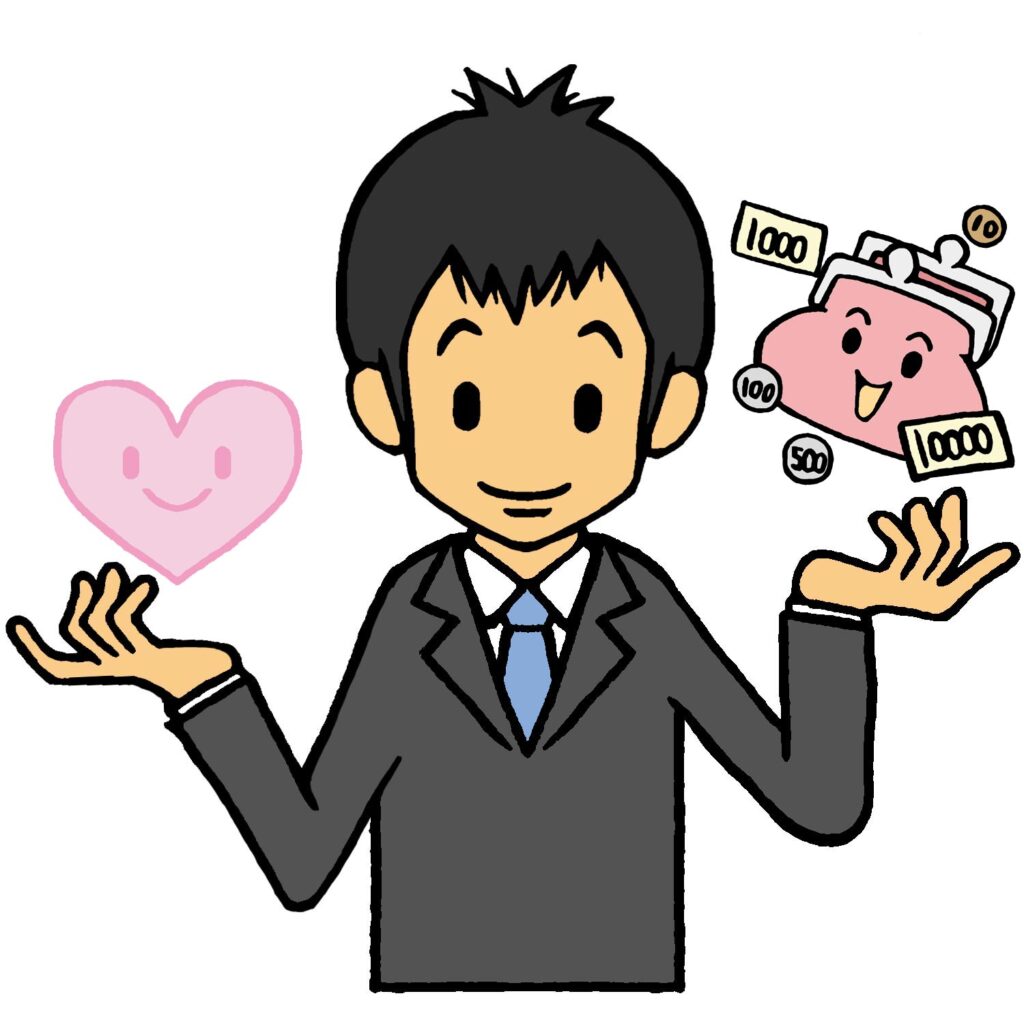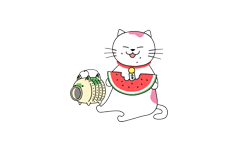【平たく解説】著作隣接権とは

(本稿は、法律用語や厳密な定義を避け、一般的な言葉で説明することを心がけています。ご了承ください。)
著作隣接権とは、著作物を世の中に伝える役割を担う人や組織を保護するための権利です。
たとえば、他人の著作物をつかって、自らの創作による別の文化的価値を加えた場合、その新たな創作の価値についての使用料を請求できる場合や、人格的な権利の保護(自分の名前を表示する/させない権利など)について定めています。
つまり、著作物そのものを創作したわけではないものの、その著作物の価値を高め、広く世の中に届ける役割を担う人たちの努力と成果を守るために、著作隣接権が設けられています。
著作権法の第四章(第89条から102条まで)には「著作隣接権」に関する定めが記載されています。
著作隣接権で保護対象とされる者は、主に「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「映画製作者」です。
「実演家」俳優、ダンサー、ミュージシャン、歌手、ナレーター、朗読家、及び舞台監督、演出家、振付師、編曲家など。
「レコード製作者」レコード会社や音楽出版社、プロダクションなど。
「放送事業者」テレビ局やラジオ局、衛星放送事業者など。
「映画製作者」映画会社や制作プロダクションなど。
なぜ著作隣接権が必要なのか?
著作権法は、文化の発展を目的としています。この目的を達成するためには、著作物そのものを創作する人だけでなく、それを世の中に届ける役割を担う人々の権利を守ることが不可欠です。
著作権が「著作物を創作した人」を保護するのに対し、著作隣接権は「著作物を世に広める役割を担う人」を保護します。たとえば、作詞作曲された楽曲は、それを創作した人(作詞家、作曲家など)の著作物ですが、ミュージシャンが、作曲家から提供された楽曲を演奏した場合、その表現力によって、原曲そのものとは別の価値を生み出します。この場合のミュージシャンによる「表現」は、オリジナルの著作物とは異なる創作的な努力の賜物です。また、出版社やテレビ局が組織力を尽くして、著作物に多大な財産的価値を付加する場合があります。
著作隣接権と文化の発展
エンターテイメント業界で活躍するフリーランスの実演家などの人権や財産的権利及び関連団体のために必要な利益を、著作隣接権によってしっかりと保護することは、安心して創作活動を続け、文化全体の発展に貢献することにつながります。著作隣接権は複雑な概念ですが、文化を支える人々を守る上で、非常に重要な役割を果たしていると言えます。