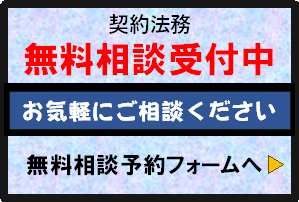【開発ベンダー向け】契約書で自社を守る!~「協力義務」を明記する~

システム開発契約書において、依頼者に協力義務があることを契約内容に明記しておくことは非常に重要です。
システム開発とは、ベンダーがユーザーからの注文を受託することによって始まります。ユーザーが注文をするときは、一般的に自社慣習又は、業界慣習があることを前提として注文をしており、何よりも「何を実現したいのか」という核となる思いがあります。
ベンダーは、要件ヒアリングでユーザーから表示された要望に従ってシステムを開発しますが、十分な品質を保つためには、開発中もユーザーからの積極的な情報提供とフィードバックが不可欠です。しかし、例えばユーザー側の担当者が人事異動や退職などによってプロジェクトから離脱して、その後任者から十分な協力が得られなくなり、紛争にまで発展してしまうケースが後を絶ちません。小職もこのようなトラブルを直接経験したことがあります。
システム開発が頓挫した時の責任負担割合については、客観的帰結として片方10割ということはありえず、ベンダーの「プロジェクトマネジメント義務」とユーザーの「協力義務」に関し、双方に落ち度があったと考えて、相応の割合で分担するのが妥当です。
プロジェクトマネジメント義務とは
プロジェクトマネジメント義務とは、ベンダーは、ユーザーの非協力や誤った関わり方によって開発作業が頓挫することのないように、適切に働きかける義務を負うことを過去裁判例1において判示されたものです。具体的には、予算・納期内で高品質な成果物を完成させるために、ユーザーとの円滑なコミュニケーションを通じて必要な協力を求め、それがないときの悪影響を説明する義務がベンダーに求められます。
協力義務とは
協力義務とは、ユーザーが、システムの開発において、ベンダーから社内資料等の提供その他システム開発のために必要な協力を求められた場合、これに応じて必要な協力を行わなければならないという義務のことです。もっとも、これはシステム開発契約特有のものではなく、例えば、建築契約における建築業者と施主との関係においても同様ですが、建築工事の場合、基本的に重要な部分については、設計段階でほぼ検討が尽くされます。一方で、システム開発の場合は、ベンダーが開発工程に入ってからも、ユーザーの協力が必要となることは多く、ここで非協力的であったり、誤った情報があれば成果物に大きな影響を及ぶことから、紛争時には特に重要な争点になります。
トラブルを防ぐために必要なこと
契約前
トラブルの芽は、プロジェクトの初期段階に潜んでいることが多く、ここでの対応が最も重要です。提案書には、開発範囲(スコープ)、前提条件、成果物、検収条件などを具体的に記載します。 見積書には、何にどれくらいの費用がかかるのか、その算出根拠を明確に示します。
契約締結時
契約内容に役割分担(ユーザーの協力義務とベンダーのプロジェクトマネジメント義務)に関する定義を明示します。この段階で重要なのは、役割分担をユーザーに丁寧に説明することです。
≪契約書の文例≫ 参考資料:一般社団法人情報サービス産業協会(JISA) 「JISAソフトウエア開発委託基本モデル契約書2020」 平成31年3月
甲:ユーザー 乙:ベンダー
第〇条(協働と役割分担)
1.甲及び乙は、委託業務の円滑かつ適切な遂行のためには、乙の有するソフトウエア開発に関する技術及び知識の提供と助言並びに、甲による仕様の早期かつ明確な確定が重要であり、甲乙の協働が必要とされることを認識し、自らの役割を誠実に実施するとともに、相手方の役割に対して誠意をもって協力する。
2.甲及び乙は、自らが実施すべき役割を遅延し又は実施しない場合、それにより生じた遅延又は不実施について、相手方に対し責任を負う。
開発工程中
プロジェクトマネジメント義務を果たす上で、最も重要なフェーズです。定期的に顧客と進捗確認会議を行い、必ず議事録を作成し、双方で合意内容を確認します。議事録は、後の「言った・言わない」トラブルを防ぐ重要な証拠となります。スケジュール通りに進んでいるか、問題が発生していないかを定期的に報告します。遅延や問題は隠さず、早期に報告し、対策を協議することが信頼関係を維持する上で重要です。議事録、課題管理表、仕様変更の合意書など、プロジェクトに関するあらゆるやり取りを文書として記録・保管します。これらの文書は、プロジェクトを円滑に進めるためだけでなく、万が一の際にベンダーの正当性を主張するための客観的な証拠となります。
納品時
事前に合意した検収基準に基づき、ユーザーにテストを実施してもらいます。 検収合格の証として、検収書に署名・捺印をもらいます。
まとめ
システム開発は、ベンダーとユーザーの共同作業です。ベンダーがユーザーに協力義務があることを事前に丁寧に説明することで、ユーザーはプロジェクトに対する当事者意識を高め、積極的な関与を促すことができます。これにより、プロジェクトの成功確率が格段に向上し、最終的にはユーザーのビジネス価値を高める高品質なシステムを、効率的かつ予算内で開発することが可能になります。
- 2004/3/10 東京地方裁判所|平成12年(ワ)第20378号、平成13年(ワ)第1739号
↩︎