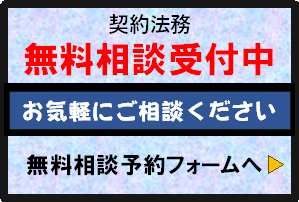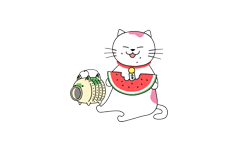【フリーランス向け】契約書で自社を守る~下請法とフリーランス法~

下請業者(主に中小企業、個人事業主又は個人)は、取引停止を懸念し、契約交渉で不利な立場に置かれがちです。受注者として、利益と心身の安全を確保するために下請法とフリーランス法の知識を持つことは、非常に重要です。発注者としても、これらの法令を軽視すれば労働基準監督署からの指導や罰則を受けたり、社会的信用の低下という商人として重大な損失につながりかねないことから、順法対応をしなければならないものといえます。
制定の背景
| 下請法 | フリーランス法 |
| 公正な取引秩序を維持することに主眼が置かれています。 かつて、優位な立場にある親事業者が下請事業者に対し、一方的に不利益な取引を強いる『優越的地位の濫用』が社会問題化していました。そうした不公正な取引を防ぐために整備された法令です。 | 公正な取引秩序を維持することに加え、個人の働き方を尊重し、保護する側面が強いのが特徴です。 働き方の多様化により増加した「フリーランス※」が、事業者との取引で不当な扱いを受けることなく、安全な就業環境を整えることを目的としています。 ※法令上ではフリーランスという表現は使わず『特定受託事業者』という文言になっています。 |
対象となる取引
| 下請法 | フリーランス法 | |
| 対象となる取引は以下の4種類に限定されています。なお、情報成果物については、更に細かく分類されます。 | 原則として全ての業務委託が対象 | |
| 【製造委託】物品の製造・加工など | ||
| 【修理委託】物品の修理 | ||
| 【情報成果物作成委託】 1.プログラムの作成 コンピューターソフトウエアの開発(設計書も含まれる) 2.映画、放送番組その他映像又は音響により構成されるもの テレビ番組、テレビCM、ラジオ番組、映画、アニメーションなどのコンテンツ制作など 3.文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの 設計図の作成、調査レポート/記事の執筆、ポスター/パッケージ類のデザインなどドキュメント、デザインの創作など | ||
| 【役務提供委託】 ビルや機械のメンテナンス,コールセンター業務などの顧客サービス代行など | ||
下請法の対象となる取引内容と資本金区分
| 取引内容 | 適用対象取引となる資本金区分 |
| 製造委託 修理委託 情報成果物作成委託(プログラムの作成) | 3億円超の親事業者(法人)と3億円以下の下請事業者(法人又は個人)の取引 |
| 1千万円超の親事業者(法人)と1千万円以下の下請事業者(法人又は個人)の取引 | |
| 情報成果物作成委託(プログラムの作成以外) 役務提供委託 | 5千万円超の親事業者(法人)と5千万円以下の下請事業者(法人又は個人)の取引 |
| 1千万円超の親事業者(法人)と1千万円以下の下請事業者(法人又は個人)の取引 |
資本金区分が同格又は、資本金1千万円以下の事業者間の取引は、下請法の適用取引にならない
対象者の定義:誰と誰の取引に適用されるか
| 下請法 | フリーランス法 | ||
| 発注者(親事業者) | 発注者と受注者の双方について資本金規模に基づいた定義があるため、規制の対象にならないケースがあります。 | 発注者(特定業務委託事業者) | 全ての事業者(法人・個人)が対象。 企業の資本金規模は問いません。 |
| 受注者(下請事業者) | 受注者(特定受託事業者) | 全ての事業者(法人・個人)が対象。 従業員を使用しない個人事業主や、代表者だけの法人(一人社長)も対象。 | |
フリーランス法では全ての事業者(法人・個人)の取引が適用されることが、下請法との最も大きな違いです。この違いにより、下請法の対象外であった「資本金1,000万円以下の企業から個人事業主への発注」や、「個人事業主から個人事業主への再委託」といったケースも、フリーランス法では規制の対象となります。
フリーランス法ならではの規制内容
フリーランス法には、下請法にはない、個人の働き方に配慮した独自の規制が設けられています。
- 募集情報の的確な表示:
フリーランスを募集する際に、業務内容や報酬、その他の条件を正確かつ最新の状態で表示することが義務付けられます。 - 育児・介護等への配慮:
契約期間が一定以上の場合、フリーランスから申し出があれば、育児や介護と業務を両立できるよう、納期や稼働時間の変更など必要な配慮をする義務があります。 - ハラスメント対策:
発注者は、フリーランスに対するパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどを防止するため、相談窓口の設置など体制を整備する義務を負います。 - 中途解除等の事前予告:
契約を中途解除する場合や、契約を更新しない場合には、原則として30日前までに予告する義務があります。
主な違いが一目でわかる比較表
表で比較してみると、下請法は日本の高度経済成長期において社会問題となった大企業などによる優越的立場の濫用を防止するため、フリーランス法は現代の働き方の多様化に対応するため、という風にそれぞれの時代背景を反映していることが分かります。
| 略 称 | 下請法 | フリーランス法 |
| 正式名称 | 下請代金支払遅延等防止法 | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 |
| 公布年月日 | 昭和31年6月1日 | 令和5年5月12日 |
| 目的 | 下請代金の支払遅延等を防止することによって、取引の適正化を図り、下請事業者の利益を保護する | 個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境の整備 |
| 規制対象者 | 資本金要件を満たす親事業者(法人) | 全ての業務委託事業者(法人・個人) |
| 保護対象者 | 資本金要件を満たす下請事業者(法人・個人) | 全ての業務受託事業者(法人・個人) |
| 資本金要件 | あり | なし |
| 対象取引 | 製造、修理、情報成果物作成、役務提供(再委託に限る) | 全ての業務委託(再委託に限らない、自社利用目的の役務提供も含む) |
| 対象外取引 | 委託者が自らの用途目的の役務の提供(自社利用目的の役務提供) 建設工事の委託(建設工事の下請負については建設業法で規定される) | なし |
| 主な規制 | 法人による不公正な行為を規制 | 全ての事業者の不公正な行為の規制に加え、ハラスメント防止、育児・介護への配慮など、個人の就業環境に関する規制も含む |
| 取引条件の明示 | 電磁的方法※で明示するときは、下請事業者の承諾が必要 | 電磁的方法※で明示するときは、委託者が選択することができるが、受託者が紙の交付を求めたときは応じなければならない |
※電磁的方法=Eメール、SNS、受発注システム、電子契約など(受託側のIT設備、ITリテラシーに対する配慮が必要)
両方の法律が適用される場合
当事者や取引内容が、下請法とフリーランス法の両方の要件を満たす場合があります。この場合は、原則として両方の法律が適用され、発注者(委託者)はより厳しい方の規定を遵守する必要があります。 例えば、資本金1,000万円超の法人がフリーランスに記事の執筆を委託するときは、基本的にフリーランス法が適用されますが、その注文を電磁的方法で行うときは、下請法の規定に則ってフリーランスの承諾が必要となります。
まとめ
下請法とフリーランス法は、どちらも優越的地位の濫用を規制することで、取引秩序を維持するためのものですが、その成り立ちや保護する対象、規制の範囲が異なります。フリーランスとして活動する個人、またフリーランスに業務を委託する企業は、両方の法律の違いを正しく理解し、適切な取引関係を築くことが重要です。特にフリーランス法については、ハラスメント対策や、育児・介護への配慮などの新たな対応が求められます。
もし、特定の業界やケースについて詳しく知りたい場合は、お気軽にご質問ください。