【平たく解説】著作物の翻案とはなんですか?
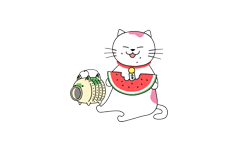
著作権譲渡契約の内容で「翻案」という文言が記載されます。この翻案とは、平たく言えば著作物をカスタマイズすることです(専門的には「支分権」として定義されますが、本稿では専門的表現はできる限り使わない方針です)。先ず「翻案」についてですが、その語意をGoogle Geminiに質問すると次の回答が表示されます。
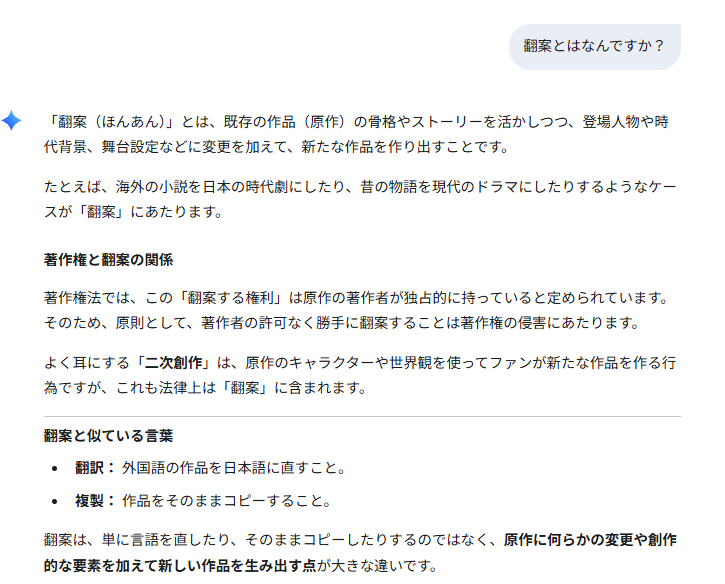
このGemini回答については、特に問題ないと考えます。
なお著作権法では、第27条で翻案権が登場します。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
この翻案権ですが、契約書作成の実務では、エンタテインメントやシステム開発などの分野で特に重要となるワードです。
なぜなら発注者が著作権の財産的価値を確保したい場合に、契約条項で「受注者はすべての著作権を発注者に譲渡する」という程度の定め方では不十分で「翻案権も含めて譲渡される」ということが契約内容に明記されていることが必要という判例1が背景にあるからです。
そのため、契約書には「著作物に対する著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)は、 から へと譲渡される。」というように翻案権(27条)も譲渡対象であることを明記する必要があります。
※第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)の解説は本稿では割愛しますが、これも明記することが重要です。
もし、契約内容にその明記がなければ、法律上は「翻案権は譲渡されず、受注者が保有している」と一旦扱うことになり、発注者がこれを覆すためには客観的証拠を提出しながら事実を証明して、それを裁判所に認定してもらわければならない、ということになる可能性があります。

- ひこにゃん事件:大阪高裁平成23年3月31日(平成23年(ラ)第56号:仮処分申立却下決定に対する抗告申立事件) ↩︎
